
今年4月、1874年創業の老舗書店「長崎次郎書店」(熊本市)が6月末で休業との情報が流れ、衝撃を受けた。書店の危機が言われて久しく、大型書店の閉店も相次いでいる。一方で、個人規模での「独立系書店」の出店は各地で続く。どうして書店をやるのか。近年は、書店に関する書籍も多数、出版されている。ここでは、どうやって書店をやるのか(ノウハウ)よりも、どうして書店をやるのか(思想)に焦点を当ててみたい。福岡市在住の記者(学芸部)の身近にある「本を巡る場」を作っている人たちを訪ねた。
本屋 月と犬
福岡市中央区のけやき通りから1本裏道を入ったその奥に「本屋 月と犬」はある。アパートの一室が店舗だ。靴を脱いで上がる。新刊と古本が半々に並ぶ棚は、冊数は少ないが、気になる本が目に留まる品ぞろえだ。「基本は自分が読みたい本を選んでいる」と店主の才松愛さん(46)。適度に古本が入ることで「自分で選んでいない本が交じるのも面白くて、(扱って)良かったなと思う」。
本は好きだが、読書家というほど本は読んでいない、と明かす。それでも本と出合ったことで、いろいろな人生、世界を知ることができた。だからこそ「本をそこまで好きじゃない人も遠ざけない本屋でいたい」と話す。来店するのは20~30代が多いという。

「若い人が本を読まなくなったと言われるけれど、うちは9割近くが若いお客さん。一人で時間をかけて本を選ぶ様子を見ているだけでうれしい」と話す。
才松さんは来店する客にあまり声はかけず、聞かれた時だけ答えるようにしている。店主を意識せず、自由に本と対話してほしいからだ。店内に置かれた「月と犬ノート」には訪れた客たちの感想や悩み、思いなどさまざまなことがつづられている。直接、言葉を交わさなくても、そんなところからもやり取りは生まれている。
才松さんは北海道出身。8歳の時、一家で熊本へ。さまざまな仕事を経験したが、一番続いたのが書店員で、紀伊国屋書店などで約8年間、福岡では書店「文喫(ぶんきつ)」でも勤務した。仕事は好きだったが、人手不足で「本をモノとして扱ってしまうような忙しさ」に限界を感じ退職。2022年9月、自身で本屋を開店した。
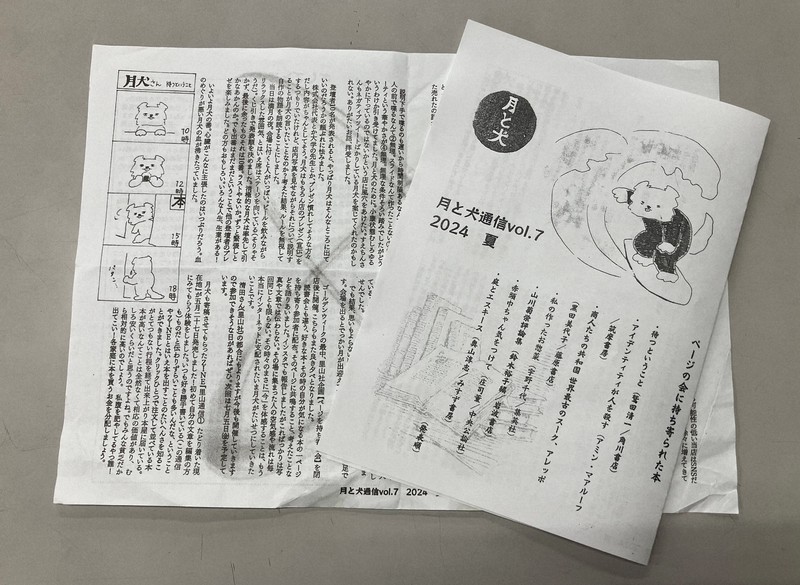
昨年1月からは、自身の近況などをつづった季刊のフリーペーパー「月と犬通信」を発行し、来店客などに手渡している。「前の号もほしい」「期間中にお店に行けないから残しておいてほしい」といった「取り置き」注文も出るなど好評だ。現在、近況のほか「おしごと漫遊記」と題して、自身の過去の仕事遍歴をつづっている。将来や仕事に悩む若者が多い中、ささやかなエールのつもりだ。
なぜ、「本屋」だったのか。繰り返し問う中で、最後にふっと才松さんが漏らした言葉に、答えがあると感じた。
「このままだと今の社会はどうなっていってしまうのか。そんな不安がある。人が一人の人間であることを見えなくさせてしまうような社会の中で、人が人であるために、本は必要なものだと思う」
ネット交流サービス(SNS)で、しつこく他人を攻撃するような閉塞(へいそく)的な社会。それは画面の向こうに人間がいることへの想像力を失っているからではないか。少し立ち止まり、自分が属する文化や正義とは異なる文化や正義が存在することを「本は教えてくれる」。
才松さんが出店に至る経緯をつづった掌編を見せてもらった。主人公は野良となった「月犬」だ。
<きっとこれでいいのかなと不安に揺れながら生きている者は他にもいるんじゃないか。集団に紛れるとわからなくなるけれど確実に一匹であるあなたと、一匹である月犬がそれぞれにこの世界をまなざしていきたい。そんな気持ちで本を売ろうと思ったのだった>(「里山通信」1号)
今年5月には、一人出版社「里山社」の清田麻衣子さん=福岡市=の企画で、店内で「ページを持ち寄る会(ページの会)」を開催した。定員6人で、それぞれが自身が感銘を受けた本の1ページを持ち寄って語り合う独自スタイルの読書会だ。少人数かつ、1ページに限定することで、参加者が抱えている問題や思いを受け止めることができ、「きちんと対話になった」と振り返る。今後も開催を予定している。
現在はアルバイトをしながら運営を続けているが、本屋だけで生計を立てることを目指す。

本屋アルゼンチン
「本はものの見方を180度変える力を持っている。だから、本を通して『世界の裏側』まで旅しようといった気持ちを込めた」。大谷(おおや)直紀さん(40)は店名の由来をそう語る。
本屋アルゼンチンは21年3月、福岡県糸島市二丈福井に開店した。JR筑肥線「大入」駅を下車し、徒歩1分。自分たちで手作りした4・5坪の小屋が本屋スペースだ。敷地内に建つ2階建ての母屋は事務所兼イベント空間で、これまでに文化人類学者の松村圭一郎さんや小川さやかさん、人類学者の磯野真穂さんらによるワークショップや、「ほぐす学び 大人の発達プログラム」などを開催。東京から会社員や弁護士、大学教授なども参加する場となっている。
6月には糸島市内に住む元図書館長の蔵書を借り、哲学者で評論家の「鶴見俊輔展」を開催した。鶴見さんが丸山真男さんらと創刊した雑誌「思想の科学」など約200冊が並んだ。
大谷さんは大阪府出身。学生時代の友人ら5人と創業した、企業の人材育成や組織開発を手掛ける会社「こっから」(本社・糸島市)の代表社員であり、本屋は、副業の位置づけだ。大学卒業後、リクルート社(東京)で働き、16年、30代で起業した。その後、九州大の社会人大学院で3年間学び、ビジネスとは対極にある知の世界の奥深さに衝撃を受けた。「ビジネスとアカデミアをつなげたい」と思ったことが、本屋開店の一つのきっかけとなった。ワークショップ開催もその一環だ。

人類学者ら5人による「働くことの人類学」実践ゼミは、座長である岡山大准教授の松村さんが各地で開催している「旅する大学」の一つとして開催した。「松村先生の方から、糸島でやりたいと連絡をいただいた」と大谷さん。ゼミには東京からも含め、約20人が参加した。糸島で五つの職場を訪ね歩き、終了後には、参加者のエッセーを小冊子「『働く』を紡ぐ旅」にまとめた。さらに、本屋アルゼンチン開店当初から「店員」として手伝う環境心理学者の南博文・筑紫女学園大学長による同行ルポも掲載されている。22年7~9月には「ビジネスパーソンと宮沢賢治を読んでみたい」との南さんの発案で講座「かたわらの賢治さん」も開講され、企業人ら13人が参加した。
今春から、南さんの蔵書約2000冊を預かり、希望者に蔵書の中からランダムに10冊を大谷さんが選んで有料で貸し出す「教授の本棚」を始めた。郵送対応で貸出期間は1カ月。今までに35人以上の利用があった。現在は一旦サービスを休止し、秋ごろの再開を予定している。

参加者の背景は考えずに本を選んでいるが「自分のために選んでもらったようだ」との感想をつづる人も多いと言う。「自分で文脈を見つける人が多く、人間のイメージする力の可能性をすごく感じた」と大谷さん。普段、自分が手に取らない本との出合いや、付箋の貼られた跡から南さんの読書の軌跡を追うなど、それぞれの楽しみ方がある。ただ並べておくだけでもいい。「物質としての本だからこそできる試み」と話す。
大谷さんは、本は「分からなさ」を味わうためにこそ必要だ、と言う。ビジネスの場では常に、簡潔で分かりやすいことが求められる。しかし、「自分の分かる範囲だけで世界を処理しようとするのが一番危険。そうなると、分からない人のことを見えないよう排除してしまう。分からない体験をすると『ああ、世界にはまだまだ分からないことがある』と思い至る。そういうことを大切にしたい」と大谷さん。だからこそ、本屋アルゼンチンは「分からなさやズレ(遊び)を届ける本屋でいたい」と話す。
ふるほん住吉
「本はずっと集めていて、でも、これまでに2回ぐらいリセットしている。全ての本を電子書籍に切り替えようと。でも、やっぱり紙の本が欲しくなってしまって」
4月に福岡市博多区住吉に古書店「ふるほん住吉」を開店したデザイナーでイラストレーターの山田全自動こと、山田孝之さん(41)はそう振り返る。
「本屋の雰囲気を楽しんだり、本を買った帰りにカフェに寄って読んだり、そうした体験全体を含めて、本が好きなんだなと思った。それが紙の本の魅力かな」
だからこそ、自身が作る古本屋も「空間が面白い場所にしたかった」と言う。本だけではなく、カセットテープや古いマッチ箱なども置き、ディスプレーにもこだわった。店内の雰囲気を演出するおもちゃなどの小物をのみの市やリサイクルショップに足を運んで集めた。お客さんが店に合わせて持ち寄ってくれたものもあり、次第に数は増えているという。

古本の魅力は「出合い」だ。客側にとっては、思わぬ掘り出し物を見つける楽しみだが、店主にとっても「新刊と違い、完全には自分で品ぞろえをコントロールできない。運と出合いによって左右される部分があり、逆にそこがいい」と語る。
秘密基地のような空間には、マンガや雑誌、映画パンフレット、カセットテープなどが並ぶ。記者も思わず、映画のパンフレットや落語の舞台を歩く「東京 落語地図」などを購入した。
本の仕入れは古本市が中心で、買い取りは今後の課題。値付けは勉強中とのことで「今は、自分だったら、この値段なら買うかなを基準に付けている。相場より安く付けてしまっているかもしれないが、そうした隙(すき)があってもいいのかな」と笑う。
棚が生み出すつながり
本棚は、その人の意識と無意識が混じり合い、脳内を映し出す鏡のようなものだ。そして、棚に並べた他ジャンルの本同士がある日、思いもしなかった結び付きを生むことがある。購入・検索履歴から機械がはじき出す「おすすめ」とは全く違う出合いだ。それは時に本屋の書棚でも起こる。だからこそ、紙の本や書店は必要なのだと、個人的には思っている。
今後も書店のほか、個人出版社や編集者など「本を巡る場」の探訪を不定期で掲載し、「本」というメディアについて考えたい。【上村里花】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



