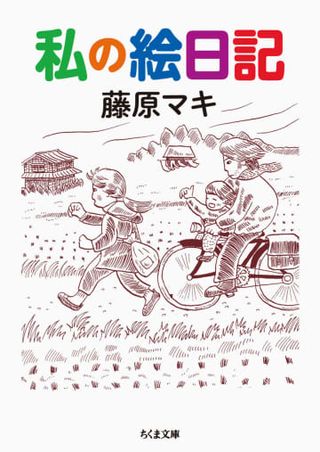束縛のない自由な俳諧
蕪村は1716(享保元)年、大阪の毛馬(けま)村に生まれた。本姓は谷氏(谷口氏とも)、後に与謝(よさ)氏を名乗る。父は村長(むらおさ)だった。母は丹後の与謝の出身との説もあるが、家業や家族についてはよく分かっていない。
20歳の頃に江戸へ出て、夜半亭巴人(はじん)に入門。日本橋石(こく)町にあった師の家に同居して俳諧を学び、俳号を宰町(さいちょう)と名乗った。巴人は芭蕉の門人・其角(きかく)や嵐雪の弟子で、自由闊達(かったつ)な俳風の人だった。「夫(それ)、俳諧のみちや、かならず師の句法に泥(なづ)むべからず(俳諧の道は、師の方法にこだわってはならない)」(『むかしを今』序文)といった教えを聞き、蕪村は「俳諧の自在」、つまり俳諧とは束縛のない自由なものだと悟ったという。俳諧は流派に縛られないとする蕪村の考え方は、巴人に導かれたものだった。
1742(寛保2)年に巴人が亡くなると、蕪村は同門の先輩俳人である雁宕(がんとう)を頼り、結城(現・茨城県結城市)に移った。しばらく北関東を放浪しながら画業と俳諧の修業を積み、東北行脚にも出掛けている。雁宕らに後押しされ1744(寛保4)年には『宇都宮歳旦帳(さいたんちょう)』を編み、初めて蕪村と名乗った。蕪村の号は陶淵明(とうえんめい)の漢詩「帰去来辞(ききょらいのじ)」の詩句「田園まさに蕪(あ)れなんとす」により「荒れた村」を意味する説が有力である。
親しくしていた結城俳壇の長老、早見晋我が1745(延享2)年に没した際には俳詩「北寿老仙(ほくじゅろうせん)をいたむ」を作った。発句とも連句とも異なる形式の俳詩は、芭蕉門人の支考によって先鞭(せんべん)をつけられ、以後江戸俳壇でも盛んに創作が試みられた。しかし、蕪村の俳詩は完成度の高さにおいて群を抜いており、詩人蕪村の素質を十分にうかがわせる。冒頭部を見てみよう。
君あしたに去(さり)ぬ ゆふべのこゝろ千々に/何ぞはるかなる/君をおもふて岡のべに行(ゆき)つ遊ぶ/をかのべ何ぞかくかなしき
(今朝あなたはこの世を去ってしまった。この夕べ、私の心は千々に乱れている。/どうしてあなたははるか遠くへ行ってしまったのか/あなたのことを思って岡のほとりに行きさまよう。岡のほとりはなぜこんなにも悲しいのか)
画家としての名声
1751(宝暦元)年、36歳の時、蕪村は京都へ移り住んだ。蕪村には専門の絵師についた形跡がなく、独学で画技を学んだと思われる。上京後は京都の寺社の画を見て歩き、丹後や讃岐へも絵画の修業に出掛けた。
18世紀の日本画壇では清(しん)の画家・沈南蘋(しんなんぴん)らの来日や画譜(画論や画法を載せた絵手本)などの出版を機に、中国南宗画(なんしゅうが)の影響を受けた新しい画風が流行した。これを「南画」という。蕪村も熱心に画譜を学び、「南画」の画家として次第に名を上げた。1771(明和8)年には、終生のライバルとなる池大雅(いけのたいが)と「十便十宜図」(じゅうべんじゅうぎず、国宝)を合作している。中国の文人・李漁(りぎょ)が別荘伊園の快適さ、自然の素晴らしさを述べた詩を基に、大雅が「十便図」、蕪村が「十宜図」を描いた。蕪村の代表作である。
この頃から画家として充実期を迎え、「富岳列松(れっしょう)図」(重要文化財)などの作品に取り組んだ。とりわけ1778年以後に、謝寅(しゃいん)の号を用いるようになってからは、「夜色楼台図」(同)、「竹渓(ちくけい)訪隠図」(同)などの傑作を描いている。

富岳列松図(部分) 愛知県美術館蔵(木村定三コレクション)

富岳列松図 愛知県美術館蔵(木村定三コレクション)
絵画と俳諧の融合
同時に俳諧師としての活動も京都で活発になった。1766(明和3)年6月には俳諧結社「三菓社(さんかしゃ)」を結成し、題詠による定例句会を開催した。出席者が合議して優劣を決める自由な雰囲気の会で、讃岐行脚で一度途切れたものの、帰京後に再開された。ここで蕪村の俳人としての技量が磨かれ、以下のような優れた作品が生まれた。
鳥羽殿(どばどの)へ五六騎いそぐ野分哉(かな)
(激しい野分の風の中、五、六騎の武士が鳥羽殿へ馬を飛ばしてゆく)
1770(明和7)には、巴人の号である夜半亭を継ぎ、京都で正式に俳諧宗匠となった。蕪村55歳の時で、プロの俳諧師としてはかなり遅いスタートだった。俳諧よりまずは画業を優先したためであろう。
蕪村の絵画と俳諧は密接な関係を持っていた。飄逸(ひょういつ)な略画に発句を組み合わせた「俳画」は、まさに蕪村の真骨頂であり、絵と句の詩情やユーモアが響き合う優れた作品を数多く生み出している。特に芭蕉の『おくのほそ道』の全文を写し、柔らかな筆致で人物の略画を加えたスタイルは、評判が高く需要が多かったようで、絵巻や屏風(びょうぶ)など複数の作品が確認されている。
蕪村の俳諧観も絵画論の影響を大きく受けていた。1777(安永6)年に執筆された「離俗論」は、以下の2点を説く。
- 心の中から俗気を消し去り、その上で句作に臨むこと。
- 俳諧にはさまざまな流派があるが、それらをみな自分のものにして、時と場合に応じ、自身の好みに合った俳諧を選ぶこと。
これは中国の画譜『芥子園(かいしえん)画伝』の画論を俳諧に応用、改変したものだった。蕪村の活躍した時代は、中国や日本の古典に学び、さらには画や書、音楽などの諸芸に遊んで俗気を脱しようとする文人思想が流行していた。俳諧もそのように精神的に豊かな境地から産み出されるものだと蕪村は考えたのである。
古典の知識に基づく知的遊戯
夜半亭を襲号して以降、蕪村一門は、『其雪影(そのゆきかげ)』(1772年)、『あけ烏(がらす)』(1773年)、『続明烏(ぞくあけがらす)』(1776年)と次々に大部な選集を出版していく。18世紀後半の俳壇は数々の流派が入り乱れ、芭蕉没後の新時代を築く気風に満ちていた。蕪村一門もまたそこに名乗りを上げたのである。ただし、これらの集の編集者は門人の几董(きとう)で、蕪村は裏から指導に当たったと思われる。
蕪村自身の編著の多くは、気心の知れた友人・門人の句を収めた小規模な冊子である。集ごとにさまざまな趣向を凝らし、あくまで自分の趣味に徹している。例えば『安永甲午歳旦』(1774年)では、門人たちの発句に蕪村が挿絵を付けているが、その絵は句意を素直に描いたものばかりではない(※1)。
雉子(きじ)啼(なく)や梅花を手折(たおる)うしろより
(雉子が鋭い声で啼いた。咲き匂う梅の花を手折ろうとしたその瞬間、後ろから)
門人の帯川(たいせん)が早春の散策を詠んだ句に蕪村が描いたのは、謡曲「羅生門」で有名な渡辺綱(わたなべのつな)が鬼に背後から襲われ、兜をつかまれる場面。渡辺綱は羅生門の鬼を退治したと伝えられる平安中期の武人である。この挿絵は一見句意とは全く関係がないが、「不意に後ろから驚かされる」といった共通点が隠されている。古典の知識に基づく知的な遊びを楽しむ蕪村の気質がうかがわれる。

早春の散策を詠んだ句に蕪村が描いたのは謡曲「羅生門」の一場面。蕪村の知的な遊び心がうかがわれる。『安永甲午歳旦』(早稲田大学図書館蔵)
また、『夜半楽』(1777年)に収められる俳詩「春風馬堤曲」(しゅんぷうばていきょく)は、自身の切実な懐旧の思いを、奉公先から帰省する若い娘の道行きに託して、昇華させた作品である。発句や漢詩句、漢詩の読み下し文などを交えた全18首から成る。途中の2首と結びの1首を抜き出してみよう。
憐(あわれ)みとる蒲公(たんぽぽ)茎短(みじかう)して乳を浥(あませり)
(いとおしくて摘んだタンポポの花。短い茎から白い乳があふれてくる)
むかしむかししきりにおもふ慈母の恩/慈母の懐袍(かいほう)別に春あり
(昔昔の幼いころの優しい母の慈しみがしきりに思われる。/母の懐には、世間の春とは別の特別な温かさがあった)
君不見(きみみずや)古人太祇(たいぎ)が句/藪(やぶ)入りの寝るやひとりの親の側
(あなたは見たことがないだろうか、故人・太祇の句を。/藪入りの休暇で帰省した子供が、一人親の側で眠っている)
最初の2つは、道ばたのタンポポを摘み、その乳のような汁から母を思い出すという連想でつながっている。3つ目は、亡友・太祇の句を引用して全体の結びとする斬新な構成。複数の詩形を組み合わせ、移り行く景色や母を思う娘の心情を描き出している。こうした実験的な試みを蕪村は自身の仲間内にだけ披露していた。それは蕪村にとって俳諧が趣味であり、心を自由に遊ばせるものだったからだろう。俳諧は町絵師として多忙な日々を送る蕪村の心の慰めでもあった。
1783(天明3)年12月25日の未明、蕪村は68歳の生涯を終えた。以下は辞世の句である。
しら梅に明(あく)る夜ばかりとなりにけり
(咲き始めた白梅のあたりから夜が明けるばかりの時となった。待ちかねた春がついにやってくるのだ)
蕪村は芭蕉を尊びながらも、蕉風を名乗る当時の平明な俳風とは一線を画し、詩情と機知を兼ね備えた句を作り続けた。墓は京都東山の金福寺(こんぷくじ)にある。蕪村自身が芭蕉ゆかりの地として芭蕉庵を再建した寺であった。
(※1) ^ 雲英末雄「蕪村の俳画を考える―「安永3年蕪村春興帖」の挿絵をめぐって―」(『文学』1996.1)他。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。