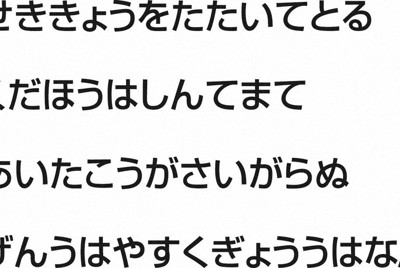放送中のドラマ『アンチヒーロー』。法律用語が飛び交う本作の根幹を支える、“法律監修”という重要な仕事がある。脚本の段階から物語に登場する法律用語に齟齬がないか、裁判シーンへの撮影立ち会い、さらには法律用語のイントネーション指導など、その仕事内容は多岐に及ぶ。
『半沢直樹』や『99.9-刑事専門弁護士-』シリーズなど、数多くの作品で法律監修を行う國松崇弁護士が考える司法の在り方とは。実際に自身が勝ち取った“無罪判決”から見えてくる刑事裁判の現実を語ってもらった。
被告人を弁護するのは“刑事司法というシステム”を守るため
「私があなたを無罪にして差し上げます」
長谷川博己演じる弁護士・明墨正樹による衝撃的なセリフで視聴者を一気に魅了した本ドラマ。ただ、罪を犯したことのない人々からすれば、弁護士はなぜ“犯罪者の味方”をするのかという疑問を抱くのではないだろうか。
刑事弁護をやっているとこのような疑問は本当によく尋ねられることで、家族からも聞かれたことがありますね。警察や検察官はその立場上、犯罪に直接関連する事実を中心に事件に向き合います。例えば、罪を認めた被疑者や被告人の動機について、「お金がなかったから」、「被害者に腹が立ったから」といった直接的なところは調べて裁判でも主張します。ところが、「なぜお金がないような生活になってしまったのか?」、「腹が立ったら人を殴るという考え方や性格はどこから生まれたのか?」という、もっと本質的な部分については、犯罪事実と直接関係がないとして、どうしてもおろそかにしがちなのです。
私たち弁護士の仕事の一つは、こうした捜査の実態を踏まえ、たとえ有罪であったとしても、その人が罪を犯すまでに一体どんな生い立ちや背景があったのか、そんな見えにくい部分にもきちんと光を当て、裁判でより公平に判断してもらうことだと思います」

さらに國松弁護士は「これはあくまでもファーストステップです」と言い、こう続ける。「刑事弁護をする弁護士は、個々の被疑者や被告人を弁護することを通じて、「この国の捜査や刑事裁判がきちんと法律に基づいた手続きのもと進められる」という刑事司法のシステムを守っていると思っています。たとえ被告人が裁判なんてどうでもいいと投げやりになったとしても、弁護士がこれに乗ってしまうとどうなるでしょうか。本来、法的には認められるべきではない証拠やいい加減に書かれた供述調書が裁判で認められてしまうことになります。
その被告人はいいかも知れませんが、その一つの悪しき前例が、他の被疑者・被告人の捜査や裁判に悪影響を与える可能性がある。もしかすると、その結果、冤罪が生まれてしまうかも知れませんよね」と語る。被告人を守る弁護士、それ即ち「裁判官や検察官、警察に対し、法に則った裁判や捜査をしてもらうためのいわば監視要員です。何かあったらいつでも闘うぜっていうスタンスを取り続けることが、司法制度を遵守してもらうための抑止力に繋がると考えています」と、その在り方を明かしてくれた。
冤罪はとても身近なものだった…!
ただ、人が人を裁くという制度がある上で避けて通れないのが“冤罪”ではないだろうか。第6、7話で描かれた個人情報流出事件は、被告人が全くの無実であったにもかかわらず第一審では有罪判決が下り、控訴審での証拠請求を不採用にされてしまう。

そんな、素人では考えられないような大きな力で真実が捻じ曲げられようとした。エンタメの世界だからと侮ることなかれ、國松弁護士は「冤罪は意外と身近にあるんです」と言う。
「冤罪が生まれるのは、個々の事件でいえば担当捜査員・検察官の油断や怠慢が原因でしょう。しかし、視点を広げれば、それはこの国の刑事司法や捜査機関の体制の問題だとみることもできると思います。例えば私の経験の中で、冤罪はニュースになるような大きな事件ではなく、世間の注目を浴びることもない、軽微な犯罪こそ起こりやすいと感じたことがありました。警察や検察の人員には限りがありますから、軽微な犯罪に対して、時間と手間をかけた緻密な捜査はなかなか行うことができないという実態があります。担当する捜査官が、他に大きな事件を抱えていたら尚更ですよね。その結果、証拠関係や当事者の証言など、裏付けが非常に曖昧な状態のまま、流れ作業のように物事が進んでいってしまいます。そして、捜査に慣れていない被疑者や被告人は、つい「そのようなものか」と安易に受け入れてしまう。これが冤罪に繋がりかねないわけです」。
起訴後の有罪率99.9%の中に実在した無罪判決
國松弁護士も、過去に担当した刑事事件で無罪判決を勝ち取っている。「経験として私が無罪判決を獲得したのは1件だけですが、実感としては、こういうことは他にも全然あり得るのだろうなと感じました」と話す。日本の刑事事件において被告人となった場合、その有罪率は99.9%という数字がある。つまり“裁判=有罪”という図式が出来上がっている中で、“冤罪”を防いだのだ。
「被害者とされた方は非常に社会的信用のある職業に就いていて、その一方、疑いを掛けられた被疑者は無職で前歴のある方でした。両者のコントラストがはっきりしている事案だったので、警察や検察官もストーリーが作りやすかったんでしょうね。被害者とされる方が“この人にやられました”と証言していること自体が重要な証拠として位置付けられており、確かに検察が出してきた証拠を見る限り、あえてそのような嘘をつくメリットもなさそうだ、と思わせる事件でした。被疑者は罪を認めず、そのまま裁判になったんですけど、第1回公判の前に、明らかに被告人の言い分の方が正しいと分かる「防犯カメラの映像」という決定的な証拠を見つけました。警察や検察はこの証拠を見逃していたんです」と言い、さらにそれが現場すぐ近くの“交番”に設置された防犯カメラだというのだから、衝撃は隠せない。

「そもそも人が人を裁くということ自体が、本当は無理があることじゃないかなと私は思っています。事件を実際に見ていない人が、後から判断しなきゃいけないというシステムが完璧であるはずがないし、間違いが起こる可能性は常にあるわけです。なのに、もしそこで間違いがあったら、1人の人生、あるいはその家族や友人の人生まで、大きく狂わせてしまうことになる。このようなリスクのある仕組みを取り入れる以上、無実の可能性を徹底的に排除し、100人に聞いて全員が間違いないと言える状況でもない限り、その人が犯人だとはいえないことにする、それを具体的に表している一つの言葉が『無罪推定の原則』だと私は解釈しています」。
さらに日本の刑事裁判というシステムについて、「人が作り上げたものだから間違いは当然起こる」とした上で、「その中で究極の選択をしなければいけないんです。例えば目の前に10人が被告人がいて、その中に1人だけ無実の人がいる。でもそれが誰かは分からない。このとき、1人の無実の人間を犠牲にして10人全員に有罪判決を下すのか、9人の犯罪者を取り逃すことになっても冤罪を生まないために全員を無罪にするのか。長い歴史の中でいくつもの冤罪が生まれ、それで苦しんだ人がいる。そのような多大な犠牲があり、日本は、後者の道こそ国民の権利を守るために必要だと判断し、選択したわけです」と教えてくれた。だからこそ「刑事司法制度の運用は堅くあるべきだと思っています」と、法を司る立場としての率直な意見を語ってくれた。

実は身近にある“冤罪”事件。ある日突然自分が被疑者になったとき、「明墨のような弁護士がいてくれたら…」と願わずにはいられないことだろう。『アンチヒーロー』で描かれている世界は現実社会と乖離しているようで、実は紙一重なのかもしれない。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。