戦後日本のアジア研究の展開
大庭 三枝 戦後の日本のアジア研究は大きく変化してきました。例えば、アジア政経学会は1953年の創立時には会員が50名ほどでしたが、その後1990年代の初め800人程度、今世紀に入る頃には4桁になりました。
石井 明 最初は日本在住の中国人研究者の方も若干はいたものの、ほとんどが日本人でした。それが外国人、特に中国からの留学生なども学会活動に加わるようになり、雰囲気も変わってきました。国籍を超えて、同じ研究者が議論し合えるという雰囲気が醸成されていったことは特筆に値すると思います。
また、アジア政経学会はその名の通り政治と経済を中心に、研究成果を出し合って議論する場として始まったのですけども、次第に社会も研究対象領域にし、最近では環境問題を議論する方も増えています。これもいいことです。
研究対象地域をみると、最初は大部分が中国関係で、それに若干朝鮮半島が加わるという状況でした。学会の「設立趣意書」には(※1)、中国のみならず、広く韓国、インド、その他南方諸地域におけるアジア問題の解明をするとされ、中国が冒頭に来ていて、それに韓国、インドが加わり、そして「南方諸地域」という言葉が使われている。当時「東南アジア」という言葉は日本でほとんど使われていなかった。「南方諸地域」というと、何か蔑称じみていますよね。最初はほとんど研究対象として取り上げられていなかった。しかし、東南アジアで国が次々に独立して、次第に国際社会で発言権を持つようになってくると、東南アジアを対象として研究を深めようという方が出てくるわけです。

石井明・東京大学名誉教授
世紀交代期におけるアジア情勢:中国への期待
大庭 先生が理事長を務められていた2001年から2003年、アジア情勢をどのようにご覧になっていましたか。
石井 20世紀の終わりから21世紀の初めという時期は、中国が国際経済とのリンケージを深めていた時期でした。1999年の11月、中国のWTO(世界貿易機関) 加盟をめぐる米中交渉が妥結する。江沢民が、これはウィンウィンの勝利を勝ち取ったのだ、と言う。それまで中国には、ウィンウィンという言葉はなかった。少なくともほとんど使われることはなかった。それをあえて江沢民はウィンウィンの勝利と言った。そうすると、その場にいたアメリカの代表団が、そうではない、トリプルウィンズだと言う。勝ったのは米中だけではなくて、グローバル経済も勝者だという意味です。
当時、国際社会は中国のWTO加盟を歓迎しました。それがグローバル経済の発展につながると考えられていたわけです。加盟が正式に承認されたのは、2001年の11月、私がアジア政経学会の理事長になった頃です。その後、外資系企業が次々に中国に進出する。海外からの直接投資も大幅に増える。中国内陸部からは、膨大な出稼ぎ労働者が―「農民工」というのですが―、沿海部の製造業で働くようになる。中国が「世界の工場」と称されるようになる。
GDP(国内総生産) の伸び率が毎年10% を超え、高度経済成長期が続いたわけです。あの時期、私は中国共産党も変わっていったと思っています。02年の11月に第16回党大会を開きますが、党規約を改正して「三つの代表論」を党規約に入れます。「中国共産党は、先進的な生産力の発展方向、先進的文化の前進方向、中国の最も広範な人民の根本的利益を代表する」という主張ですが、ポイントは私営企業家の入党を認めたこと。もともと中国共産党は労働者農民の政党であり、階級闘争を叫んできた政党です。けれども、その階級政党から脱皮して、資本家を含む広範な中国人民を動員して、豊かな国をつくっていくという道を歩み始めた。
この第16回大会の初日に、『人民日報』は「時代とともに進む」(「与時倶進」)と題する社説を掲げました。時代とともに進むというのは、マルクス主義は時代が経つに従って発展していく、だから政策は時代の流れに沿って変えていいのだという主張です。要するにどのような政策変更も時代とともに進むという言い方をすれば、正当化される。そういう主張が、中国共産党の中で受け入れられるようになったわけです。
あの頃は、中国は変わっていく、国際社会と協調してグローバル経済の一員として発展していく、昔の階級闘争に囚われた政党ではなくて、資本家も党内で活躍できるようになる、そう考えて研究を進めた方が多かったように思います。今から考えれば、楽観的過ぎたのではないかという反省はありますけども、中国の変化を歓迎する気持ちは当時強かったですね。
それから、胡錦濤時代は対外的には融和的な姿勢を取る傾向があって、日中間にもいろんな問題は生じてはいましたが、それほど尖鋭化しなかった。確かに胡錦濤時代の最後の方では、軍事強国を目指すというような議論も出てきてはいましたが、それほど表面化はしていませんでした。
軍事大国化の方向に大きくかじを取ったのは、やはり2012年に習近平がトップになって以降です。それまでの中華人民共和国の歴史を振り返って、毛沢東時代は立ち上がる時代だった、鄧小平時代は豊かになろうとした時代だった、われわれ習近平の時代は強くなるのだということを、内外にはっきり宣言する。そして、実際にそれを目指して内外政策を進めるようになったわけで、習近平の時代になって変わったという面が強いですね。
香港から大陸へ「現場通い」
大庭 ご研究を振り返って、先生が大切にされてきたことを教えてください。
石井 私の学生のころ、現代中国を研究するツールは全然なかった。今では、朝6時過ぎに目を覚ましてネットを立ち上げれば、その日の『人民日報』を読むことができます。私の学生のころは、3カ月ぐらい経ってから船便で『人民日報』が日本に届くという状況でした。生の中国語を聞く機会もほとんどない。それで、短波放送の聴けるラジオを買ってきて北京放送、中国では中央人民放送と言いますが、それを聴く。でも雑音が入り、あまりクリアに聴けなかった。そういう時代だったわけです。
広い中国大陸を旅行してみたいという気持ちが強くなりました。しかし中国に行く機会がない。機会がやってきたのは1979年に1年間、香港中文大学に留学したときです。79年というと、鄧小平が改革開放政策を始めた時期です。大都市に限られてはいましたけれども、外国人が旅行、観光旅行に行けるようになった。それで79年には何度も香港から、香港人が内地と呼ぶ大陸に出かけて行ったわけです。台湾に行ったのも79年が最初です。
私の好きな言葉に「千里の道を行くは万巻の書を読むに勝る」があります(※2)。研究対象地域はできるだけうろついた方がよいと思っています。79年以来そうしてきたわけで、私は自分のことを現場主義者と称しています。
国境という現場
大庭 石井先生が2014年に岩波書店から出版された『中国国境―熱戦の跡を歩く』も、現場主義に従って各地を回られて体験し、お考えになったことが反映されている本ですね。また最初の単著である『中ソ関係史の研究―1945–1950』(東京大学出版会、1990年)とつながっているのでしょうか?
石井 その通りです。中ソは同盟関係から始まって、その後国境で戦うようになる。しかし、時間をかけて紛争を解決していった、そのいい例なのです。中ソが紛争を解決していったケースというのは、他の国境紛争の解決を模索する上で参考になると考えてきたわけです。
国境紛争はそう簡単に解決できるわけではない。紛争をmanage (管理)する段階と、それからsettle(解決)する段階と、2段階のプロセスとして考えなければならない。最初はまずマネジメントで、これ以上紛争をエスカレートさせない、そのためには何をしたらよいのかということを考える。尖閣の紛争もすぐに一直線に解決を目指すことは無理で、やはり事態をコントロールする、マネージする、そのためには何ができるかということを考えてゆくのが大事だろうと思っています。
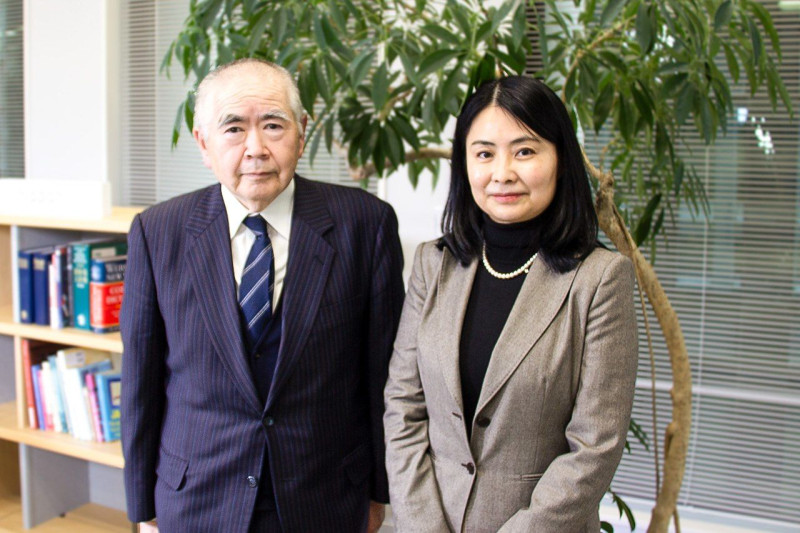
石井氏(左)と聞き手の大庭三枝・神奈川大学教授
日中国交正常化と昭和天皇の「お言葉」
大庭 先生はいくつかの著作で、日中国交正常化後、1973年4月3日に初代中国大使小川平四郎が信任状捧呈のために国家主席代理の董必武と会談をした時に、小川大使が「昭和天皇のお言葉があった。それは、『日中に不幸な歴史、戦争があったことを遺憾に思う』といった謝罪の言葉があった」と述べたと指摘しておられます。
石井 昭和天皇には何とかして中国との関係を大事にしたいという気持ちがおありになった。「遺憾」という言葉を使ったメッセージを中国側へ送ろうとされた。けれども、側近は乗り気でないわけです。たまたま、小川大使と昭和天皇は面識があった。昭和天皇に対して小川大使は進講したことがあったわけです。それで昭和天皇のイニシアティブで、側近の躊躇(ちゅうちょ)する動きを抑えつ、小川大使を通じて中国側に自分の気持ちを伝えた。昭和天皇のお言葉は、私が外交記録の開示請求を出し、2013年3月22日付で開示されたのですが、もっとこのエピソードは日本で知られてよいと思っています。
インタビューは、2023年2月10日、nippon.comにおいて実施。原稿まとめを大庭三枝・神奈川大教授と川島真・東大大学院教授が担当した。『アジア研究』(69巻4号、2023年10月)にインタビュー記録の全体が掲載されている。
(※1) ^ 「学会設立趣意書(1953年)」
(※2) ^ 元々は董其昌の言葉「讀萬卷書,行萬里路」。その後意味が変容して「讀萬卷書,不如行萬里路」となったと考えられる。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。



